幼い頃の薄ぼんやりした、だけど輝いてる思い出って誰にでもあるだろう?記憶の隅にひっそりと佇む、埃をかぶった綺麗なガラス玉みたいなもの。
すっかり物の増えた心の部屋にあるそれを引っ張り出して汚れを払う機会があるかは人によるだろう。でも、もし君がそれを見つけて今の自分と繋ぐことが出来たのなら、それはきっととても幸せなことなんだろうね。
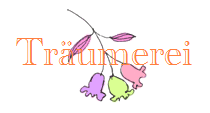
ナポリの下町は今日も朝からにぎやかだ。
世間話に盛り上がる地元住民の声や、時折聞こえる観光ガイドの英語。道を隔てて向かい合うアパルトメントの間にかかった洗濯紐に下がる色とりどりの洗濯物は、白と青の混じる空を背にはためいて通行人の頭上を彩っている。ナポリ湾からの潮風が僕の前髪を揺らして上へと昇っていくのに釣られて空を見上げると、太陽を背に飛ぶウミネコが見えた。
パッショーネに入ってからの日々は決して平和でも穏やかでもないけれど、こうやって歩く街並みは一般人だった頃と変わらずに眩しいくらいの彩りに溢れている。
「フーゴ……?」
この天気なら頭上にはためく洗濯物たちもあっという間に乾きそうだ。そんな事を思いながら歩いていた背中に声がかかった。雑踏に紛れそうな大きさの澄んだ声はどこか懐かしい響きがする。
振り返った目に映ったのは可愛らしい女の子だった。僕と同じ年頃に見える彼女は振り返った僕の顔を見て少し不安げだった顔をぱっと明るくする。僕の名前を呼んだのは間違いなく彼女らしいが、親し気にされる覚えがない。首を傾げそうになったところで、脳裏に浮かんだ名前に僕ははたと動きを止めた。
「……もしかして、?」
「やっぱりフーゴだ!」
半信半疑での問いかけに笑顔で駆け寄ってくる姿に、記憶の中の小さな女の子が重なった。
と僕はいわゆる幼馴染みというやつだ。お互いの家が近く、小さい頃にはよく遊んでいた。の家も僕の家も、いわゆる名家というものになるんだろう。大人は周りにたくさんいるけれど、同じ年頃の子供と遊ぶ機会はあまりない。お互い、屋敷のように大きな家で子供一人なのが寂しい事をよく知っていた。数少ない友達であると二人で遊ぶ時間は、幼い僕にとって何よりも楽しい時間だった。
少し成長して小学校へと入ると、と過ごす時間は極端に少なくなった。通う学校が違ったというのもあるが、僕の頭が少しばかり優秀だと分かり期待した両親によって学校から帰った後も勉強をさせられるようになったことが大きかった。お互い新しい友達ができていたからそこまで寂しいということはなかったけれど、やっぱり小さい頃からよく知っている幼馴染は他とは違う。が休日に時々家へと遊びに来てくれると、ひどく嬉しかったのを覚えている。
中学校に入ると交遊関係も広がる。また学校が違ったことも相まって、と会うことはほとんどなくなっていた。時折、学校から帰ってくる姿を自分の部屋の窓から見るだけ。大切であることは変わりないけれど、と僕の間柄は「ずっと仲のいい幼馴染」から「小さい頃は仲が良かった幼馴染」に変わりかけていた。……それを僕が、全く望んでいなかったとしても。
13歳で僕が飛び級で大学へ入ってからはを見かけることさえなくなった。家が近いといっても隣同士というわけではなかったし、僕は大学、は中学と学校の形態が違う分生活リズムも異なる。僕の場合中学校から大学へ急に上がったせいで勉強のレベルも格段に上がり、忙しさは以前とは比べ物にならないほどだった。二人で遊んだ幼い頃を思い出してそれを懐かしむ時間だけが、勉強に追われる生活の中で唯一心が休まる時だったかもしれない。
そしてせっかく入った大学で僕が不祥事を起こして退学処分になり親から勘当されると、ぼくとの繋がりは完全に切れた。
最後にまともに会ったのは小学生の頃だから、5年ぶり。……5年、だ。自分の中で噛み締める様に、その事実を反芻する。大人になってからでもきっと5年という歳月はそれなりに長い。11歳から16歳へと変わる5年間なら尚更だ。
離れている間に、は“かわいらしい”から“美しい”という言葉がより似合うような姿へと成長していた。少女と女性の狭間のようで少し不安定な、そしてその危うさこそが源である美しさ。すらりと伸びた手足も、細面に納まる涼しげな目や通った鼻筋、そしてそれを縁取る輝く髪も。最初に声をかけられたときは気付かなかったけれど、改めてちゃんと見ると一瞬息を呑むような凛とした美しさをまとっていた。
言葉の出てこない僕をまっすぐに見つめて、は笑った。
「久しぶりだね」
「……ああ」
懐かしむように目を細めて微笑まれるとひどく心がざわつく。決して昔に戻れるわけなんてないのに、自分が11歳の少年に戻ってしまったみたいで落ち着かない。
あいまいに言葉を返すと彼女は少しだけ距離を詰めて僕の目を覗き込むように首を傾げた。
「少し話せない?」
「……少し、なら」
「良かった」
安心したようにそう言って、はまた笑った。僕の知っていた頃と変わらない、屈託ない笑顔で。
・・・
「ここでいいよね」
「……」
近くにあったバールに入るなり迷わずテーブル席へと向かったに思わずため息をつきそうになった。僕より先に店内に入って、カウンター席へと近づく時間すら与えなかった。少しと言ったくせに話し込む気なのを隠すつもりすらない。諦めて向かいに座りウェイターを呼ぶと、満足げな微笑みがの顔に浮かんだ。
「エスプレッソ」
「それだけでいいの? はラテマキアートとクロワッサンで」
ずらりと並ぶ飲み物と食べ物の名前。簡潔に伝えてにメニューを渡すと訝しげな視線が返ってきた。朝ごはんまだなの、と言う彼女にまたため息をつきそうになるのを抑える。僕だって朝食はまだだ。ただ長居したくないという意思を示したくて、空腹を訴える胃袋を無視しただけだ。気を付けないと漂うペストリーやパニーニの良い匂いに腹が鳴りそうだ。
「ずっと会いたかった。ずっと探してた」
メニューを下げられ二人の間を遮るものが無くなるやいなや、はそう言った。なんの躊躇いもごまかしも無い、まっすぐすぎるくらいの言葉。今の僕が向き合うには、眩しすぎるまっすぐさ。
「……僕は、もう君の知っていた子供とは違う」
苛烈な色をまとう目から視線を逸らしての後ろ、ガラス越しに見える通りを眺めた。
大学から退学になって勘当されただけじゃない。僕はギャングになった。別にパッショーネの一員ですと書いてある看板をぶら下げて道を歩いているわけじゃないけれど、裏社会に属する存在なことは確かだ。
イタリアにはギャングが溢れている。普通に暮らしている、普通に見える男が実はある組織の幹部だった、なんてことがザラにある。だから別にギャングが一般人とは付き合わないようにするなんてことは全くない。だけど、は名家の娘だ。僕みたいに落ちぶれた、後ろ暗いところのある男と仲良くするべきじゃないんだ。僕のためにも、彼女のためにも。
そう全てを口にはしなかったけれど、なんとなく言いたいことは分かったんだろう。こちらを見つめるの目は怒りに燃えていた。
「だから何?もしかしてがずっと名家のご子息だから仲良くしてるとでも思ったの?お家が良くなければ親しくする気なんて微塵もないって言い放つ、薄情な奴だと思ってたの?」
そんなわけない、と口にすることはできない。その通りだからだ。が優しいことなんて小さい頃からよく知っていたけれど、それでもすっかり全て失った僕を見放さないでくれるという確信を持つことはできなかった。名家の子息という肩書も飛び級での大学入学という名誉も無くなって、それでも前みたいに僕を認めてくれるか怖くて仕方なかった。だから勘当された後はの家には決して近づかず、連絡を取ろうともしなかった。
怖かったんだ、僕は。
ぐ、と言葉に詰まって俯いた僕を見て、は寄せていた眉を下げた。
「それとも……フーゴは子供の頃と仕方なく友達をしてたの?いい家のお嬢さんだからとりあえず仲良くしておこうって、そう思ってた?」
「……そんなわけないだろ」
「でしょ? だってそう」
「でも僕は、」
「知ってるよ、フーゴが今何をしてるのか」
遮る言葉に血の気が引いた。
「言ったでしょ、ずっと探してたって。だからフーゴが今どんなところに属してて、どんな人たちと一緒にいるのか知ってる」
淀みなく紡がれる言葉にどんどんと指先から温度が消えていく。鉛を流し込まれた心臓が送り出す血が体を巡り全身を冷たくする。なんとか口を開いても、渇き切ったように張り付いた喉の奥が声を発するのを拒む。どこからかカタカタとなる小さな音にゆっくりと目を下げると、テーブルの上で固く握ったこぶしが震えていた。
わななく唇を開いたまま言葉を失くした僕をただ静かに見つめて、はすっかり冷たくなった僕の手に自分の手を伸ばした。
「それでも、フーゴと一緒にいたいの」
形のいい唇が紡ぎだした言葉に瞠目した。包み込む柔らかい手は縋りつきたくなってしまうくらいに温かい。
そんな、そんなの、
「嘘、だ」
やっとの思いで絞りだした声は周りの客の喧騒に紛れてしまいそうなくらい掠れていた。
きっとこの頭は、ずっと望んでいた温度に触れておかしくなっている。そんな事あるはずがないのに、心の奥底で欲しがっていた言葉を聞いたと勘違いしている。
「僕の存在は君のためにならない」
後ろに引こうとした手をしっかりとした力で引き留められた。細い指は華奢なくせに自身と同じで頑固だ。
「はパンナコッタ・フーゴっていう人のことがずっと大切で、大好きなの。どんな肩書を持っていてもそれは変わらない。それは、信じてほしいよ」
じんわりと伝わる熱が冷え切った指先を段々と温めていく感覚に鼻の奥が痛む。
何度、何度そう言われることを妄想しただろう。いつかとまた再会して、彼女が僕の今の状況を知っても昔と変わらずに接してくれたらどんなに幸せだろうと。それなのに、いざ願った言葉を聞くとそのあまりの都合の良さに痛みばかりが広がった。ギャングである男と名家の子女がどうやったら釣り合うって言うんだ。
「嘘だ」
「ねえ、聞いて」
子供を諭すような、優しいけれど有無を言わせないような口調で呟いて、は握った手をゆるく揺すった。
「前から思ってたんだけど、の両親は既にギャングと何らかの関係を持ってると思う。ある程度有名な人間は、裏社会との繋がりを持つことを避けられないから」
「!」
「だからきっとフーゴを避ける必要なんてない」
の言ってることは全く的外れなわけじゃない。金が集まるところに裏社会の連中は集まる。汚職などしていない人物でも、大きな企業や政治家が全くギャングと関わらないなんてことはほぼ有り得ない。好むと好まざるとに関わらず、ギャングは大きな金の動く場所には必ず現れる。
の両親は心の広い、優しい人々だった。けれど同時に昔から続く大企業を同族経営している人々でもあった。裏社会とある程度の関わりがあったとしても不思議じゃない。もしかしたら、が僕の現在の状態を知ることを手助けすらしたかもしれない。……それでも。
「……僕のせいで君の人生になんらかの支障が出たら死んでも詫びきれない」
「確かにギャングはまともな仕事じゃないかもしれないけど、それでもフーゴがいない方がの人生に支障が出るよ」
奥歯を噛み締めた。
なんてずるい女なんだ。ずっと離れていたくせに、5年ぶりに会ったっていうのに、簡単にそんなこと言いやがって。離れたばかりの頃どれだけ僕が君を恋しく思っていたか知らないくせに。同じ年頃の君に似た女の子を見る度に息が止まりそうになったのを知らないくせに。
「頼むよ、」
食いしばった歯の隙間から声を絞り出す。一度縋ってしまったら、二度と手放せなくなる。だから、戻れなくなる前に離してくれ。頼むから。
「ラテマキアートとエスプレッソです」
ウェイターの声にはっと我に返った。彼は決して甘くはない雰囲気で手を握り合う僕たちを訝しげに一瞥してテーブルにトレイを置いた。銀色のそれがテーブルの空いた部分を狭めても、は気にせず僕の手を握ったままでいる。
「やっぱり、僕は」
「お願い。にはフーゴが必要なの」
柔い熱はまた手を握る力を強める。きっと本気を出せば振り払える力なのに、もう僕はそれをしたくなくなっていた。
嘘もごまかしもない目で薄汚れた僕を見て、喉から手が出るほどに欲しかった言葉をこんなに簡単に繰り返しくれる。昔焦がれたそのままの力強さで、僕の心を攫っていく。それを振り切る力はもう残っていなかった。
「本当に、いいのか」
「何度聞かれたって答えは変わらない」
なんの躊躇いもない、どこまでも揺るがない返事。泣きたいような気持ちで目を閉じた。ああ、もう戻れない。僕はもうきっと自分からを手放せない。
小さな手を一度離して僕からまた繋ぎ、白魚のような指を絡めとった。
「……嫌だって言っても、もう離れないからな」
「そうして。だって離す気ないから」
精一杯の虚勢を流す言葉はどこまでも優しい。馬鹿みたいに喉の奥が震えて目の前が歪みそうになるのを必死に抑えようと俯く僕の顔にもう片方の手をそっと添えて、はそろりと頬を撫でた。
「ねえフーゴ、また会えて本当に嬉しい」
甘い言葉に上げた顔を熱っぽい視線で射抜いては艶然と微笑んだ。
「ここのクロワッサン、本当に美味しいんだよ。のが来たら半分食べない?」
情けなくも赤くなった僕の顔を愛しげに見つめる彼女は、くらくらするくらい魅力的だ。